こんにちは!梅雨に入ったと思ったら、あっという間に猛暑がやってきましたね💦💦
昨日来局された患者さんが、寝ている間に熱中症になってしまって大変だった、というお話をされていました。私も数日前、炎天下の中自転車で1時間くらい外出していたら、帰宅後頭痛が…慌てて水分、塩分補給しました(>_<)
この時期、本当に注意したい「熱中症」。誰にでも起こりうる危険な症状ですが、正しい水分補給を知っていれば、しっかり予防することができます。今回は、中医学はお休みして、昨年勉強した「飲水学」をもう一回復習して、効果的な熱中症対策をお伝えしますね~
飲水学とは?
飲水学というのは、「脱水にならないための正しい知識」のことで、横浜市東部病院の谷口秀喜先生が名付けられました。熱中症や脱水症は、死に至る病気の中で、唯一自分自身で予防できるもの。今後、暑くなることはあっても、夏の気温が下がることはない時代に、この予防が本当に大切だとお話しされていました。ではその飲水学の内容を詳しく解説していきます。
熱中症と脱水

熱中症とは、以前のブログでお伝えししたとおり、暑い、湿度が高い環境で起こる体調不良のことで、脱水症と異常高体温によっておこります。体は体温が上がった時に汗を出すことで、体温を下げようとしますが、大量の汗が出ると、体に必要な水分や電解質(塩分など)が足りなくなり、それが進むと脱水症になります。脱水症になると、熱を逃す働きが弱くなり、さらに体温上昇を引き起こします。脱水症の影響を受けやすい臓器としては、脳・消化器(胃・腸)・筋肉が挙げられます。
脱水症の症状
脳に脱水症が起きると、「めまい」「立ち眩み」「集中力・記憶力の低下」「頭痛」「意識消失」「けいれん」など、消化器官では、「食欲低下」「悪心・嘔吐」「下痢」「便秘」など、筋肉では、「筋肉痛」「こむら返り」「しびれ」「麻痺」のような症状が出現します。特に子供と高齢者は脱水症になりやすいので注意が必要です。
👉子供が脱水になりやすい理由
①成長期は水分を多く必要としやすい
②体重当たりの不感蒸泄(皮膚や呼吸から失われる水分)が多い
③汗をかく機能や腎機能が未熟、
👉高齢者が脱水になりやすい理由
①体液をためる機能を持つ筋肉が少ない
②飲食量が減っている
③のどの渇きや暑さに気が付きにくくなる
熱中症予防に効果的な水分補給のポイント
1. 1日8回に分けて飲む
必要な水分量を、1日に8回に分けて摂りましょう。具体的には、起きた時、食事の時、食事の間、入浴の時、寝る前です。水以外に、お茶やコーヒーでも大丈夫。
2. のどが渇く前に飲む
のどの渇きを感じたときには、すでに体の水分は不足気味です。
こまめに水分補給することが、熱中症予防の基本です。
3. 一気飲みはNG!少しずつが吸収に◎
一気に大量の水を飲んでも、吸収が追いつかず、尿として出てしまうことも。
▶注意点
- 1回につき100~200mlが目安(体重60kgの人で1日の摂取量は1200ml必要です)
- 常温または冷たすぎない水がベスト。アルコールはNGです。
脱水症の時の水分摂取法
まずは経口補水液を500mlすぐに飲みましょう。それで症状が改善したら、その後さらに500mlほどをちびちび飲んでいきましょう。自力で飲めない、もしくは意識レベルが低下しているような場合は、すぐに病院に搬送しましょう。
経口補水液について

最後に、経口補水液について補足します。500mlにつき塩分は1.45g入っています。普段の水分補給としては、塩分が多いためおススメできませんが、食欲がなくきちんと食事を摂れていないときは、1食分1本の経口補水液を飲むのがよいとのこと。また、「体が脱水しているときは美味しく感じられる」と言われていましたが、今は味が改良されていて、脱水でなくてもおいしく感じられるそうです。お年寄りで、水を飲むとむせてしまう場合は、ゼリータイプがおすすめです。
まとめ
熱中症には塩分も大事、とよく言われますが、先生によると、日本人は塩分を食事でしっかりとれているので、通常の場合は塩分タブレットは必要ないということでした。逆に、食欲が低下している方は、意識的に塩分を取らないといけないですね。最初の患者さんも、体重コントロールのため、1日2食だったとのことで、食事や塩分に気を付けるようアドバイスしました。
また、スポーツドリンクは、普段飲むには糖分が高いので半分に薄める、原液は運動時などたくさん汗をかくときに限定するほうがいいそうです。水分補給にも、日常的、非日常的と使い分けが必要ですね。
熱中症は、知識と習慣で防げる症状です。
飲水学の知見を取り入れて、日常的に水分補給を意識することで、夏バテや体調不良の予防にもつながります。「のどが渇いたら飲む」ではなく、「体のために飲む」習慣をはじめて、猛暑の夏を乗り切りましょうね(^^)/

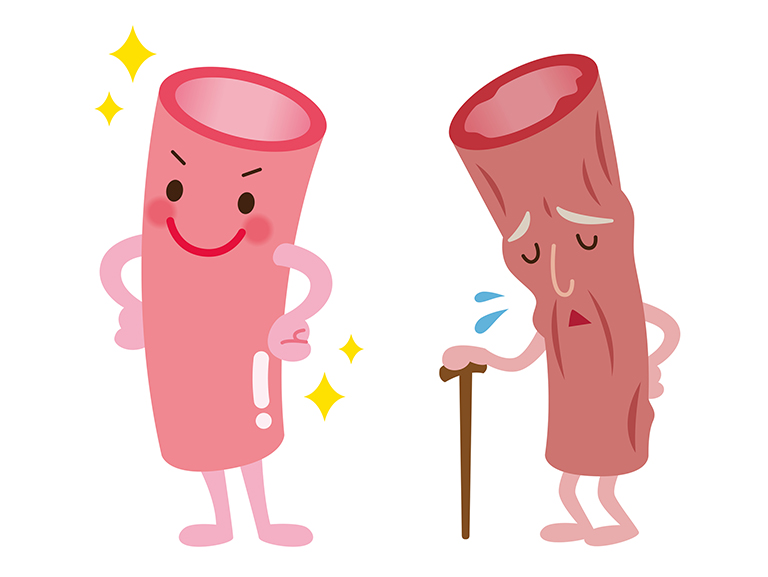

コメント