先日テレビを見ていたら、「夏休み時差ぼけ」という特集をしていました。比較的長い休みがあった後に普通の生活に戻るときに起きやすい症状で、もうすぐ2学期を迎えるお子様ばかりではなく、盆休みの後など長めの連休後にも起こりやすいとか。かく言う私も、この2週間ほどほとんど働かず遊びほおけていました(^^;今週月曜日、久しぶりの出勤がつらいのなんのって…
さて今回はこの休み明けの不調の原因と養生法を、西洋医学と中医学の視点から考えてみましょう。
夏休み時差ぼけ

夏休みや長期の休暇は、心身をリフレッシュする大切な時間です。ところが、休み明けになると「体がだるい」「頭が重い」「朝起きられない」といった不調を訴える方が少なくありません。これはいわば、“社会的時差ぼけ”ともいえる現象です。意欲の低下や不安など、精神的な面だけではなく、全身の倦怠感や頭痛、食欲不振など体調面にも不調があらわれることがあるといいます。 この「夏休み時差ボケ」に拍車をかけているのが今年の記録的な暑さだそう。冷たいものの食べ過ぎや、お休み中の暴飲暴食で胃腸が弱っている場合が多く、さらにこの暑さで自律神経が乱れがちな場合が多いです。「腸脳相関(ちょうのうそうかん)」といって、自律神経と腸の状態は密接につながっているため、体調や精神面にさらに影響が大きく出ます。この状態を、西洋医学、中医学の観点から見ていきましょう。
西洋医学からみた休み明けの倦怠感
原因
- 長期休暇で生活リズムが夜型に傾き、睡眠・覚醒のリズムがずれる
- 睡眠不足や睡眠の質の低下が溜まる「社会的ジェットラグ」
- 不規則な食生活、運動不足、アルコール摂取の増加
- 自律神経(交感神経と副交感神経)の切り替えがうまくいかず、だるさや頭痛を感じやすくなる

養生のポイント
- 朝の光を浴びる:起床後すぐにカーテンを開け、体内時計をリセット
- 睡眠習慣の回復:休み中より30分~1時間早く寝る習慣を戻す
- 軽い運動:ウォーキングやストレッチで血流を改善し、交感神経を活性化
- バランスのよい食事:炭水化物に偏らず、たんぱく質・ビタミンB群を意識
中医学からみた休み明けの倦怠感
原因

- 夜更かし・暴飲暴食は「脾(消化)・胃」を傷め、だるさや重さの原因に
- だらだら過ごすと「気」が滞り、心身がシャキッとしなくなる
- 休み明けの精神的ストレスは「肝気」を乱し、疲労感や気分の落ち込みを招く
養生のポイント
- 脾胃を整える食養生:おかゆ、スープ、山芋、なつめ、豆類など。冷たい飲食を避ける
- 気を巡らせる:軽い散歩やストレッチ。アロマや呼吸法でリラックス
- 漢方薬の一例:
・倦怠感が強い → 補中益気湯
・気分の落ち込み → 加味逍遙散
・消化不良・胃もたれ → 六君子湯
夏バテ・夏の疲れに効く足つぼ

1. 湧泉(ゆうせん)
- 足裏の土踏まずの少し上、指を曲げたときにへこむ所。
- 効果:全身の活力を高め、疲労回復・だるさ改善。
2. 太陽神経叢(たいようしんけいそう)
- 足裏の真ん中あたり、土踏まずの中央。
- 効果:胃腸の働きを整え、消化不良や食欲不振に。
3. 胃・脾(い・ひ)の反射区
- 足裏の土踏まず全体(特に内側)。
- 効果:胃のもたれ・食欲不振・消化不良に。
4. 腎臓の反射区
- 足裏の真ん中より少しかかと寄り。
- 効果:水分代謝を助け、むくみや疲労回復に。
5. 三陰交(さんいんこう)
- 内くるぶしの上、指4本分の位置、すねの骨の後ろ側。
- 効果:血流改善、ホルモン・自律神経のバランスを整える。夏の冷えやだるさにも◎
ツボの押し方
- 親指やツボ押し棒で 3~5秒押して離す を繰り返す
- 強すぎない心地よい圧で
- 足湯やお風呂上がりに行うと効果UP
まとめ
夏休み時差ぼけの解消には、西洋医学では自律神経・体内時計を整えることがポイント、中医学では「気血を養い、湿を取り除き、心身を安定させる」ことが大切ですね。まずは、しっかり睡眠をとること、そして、休み中の暴飲暴食ですっかり弱ってしまった脾胃にやさしい食事を心がけるようにします。また、遊びすぎ?で、ひざや腰の痛みが出ていたり、急に仕事復帰したら世の中のリズムについていけなくて、気分が少し落ち込み気味です(^^;湧泉のツボをおして、やる気復活を目指したいと思います💪
私のような、夏休み時差ぼけや夏の疲れがたまってぐったりしている方も多いと思います。無理をせず、少しずつリズムを取り戻す工夫をして、秋に向けて元気に過ごせるよう心身を整えていきましょうね~(^^)/
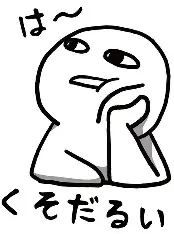


コメント