
庭のアジサイがきれいに咲きました。昨年咲いた後、まったく手入れをしなかったので、今年はあきらめていましたが、真っ白な大きいお花がたくさんです✨今年こそ、きちんとお手入れするぞ!とずぼらな自分を反省しています^^;
昨日のブログの中で、梅の「酸味」について軽~くお話ししました。せっかくですので、今回は中医学から見た食品の味=五味、それから、体に対する作用=五性についてお話ししたいと思います(^^♪
五味
薬膳では、「酸」「苦」「甘」「辛」「鹹(かん)」の5つの味を「五味」と言います。それぞれ特有の働きがあると考えられて、体への良い影響もあれば摂り過ぎると不調を起こすこともある、とされています。
「酸味」
梅を代表とする酸っぱい味のことで、「肝」に働きかけて、自律神経の働きを整え、ストレスを解消する作用があるとされます。また、正常な体液を体内にとどめ、出過ぎるのを防ぐ作用があるので、寝汗、下痢、頻尿などに効果的です。
「酸」の主な食材
レモン、トマト、ザクロ、イチゴ、ミカン、リンゴ、梅、米酢、黒酢 など
「苦味」
ゴーヤのような苦い味のことで、「心」に働きかけます。からだの熱を取る作用、からだの余分な水分を乾かす作用、からだの老廃物や病邪を取り除く作用があるとされています。高温多湿な地域や、湿度が高くて暑い夏に大活躍です。
「苦」の主な食材
セロリ、ゴーヤ、 クワイ、キュウリ、パセリ、フキ、緑茶など
「甘味」
カボチャやサツマイモなどの甘い味のことで、「脾」に働きかけ、疲れ、虚弱を改善したり、痛みを和らげ痙攣や緊張を緩める作用があります。また味全体をまとめ、栄養分を吸収しやすくする働きがあります。
「甘」の主な食材
カボチャ、ジャガイモ、トウモロコシ、山芋、ニンジン、牛乳、バナナ、ハチミツなど
「辛味」
唐辛子などぴり辛い味のことで、「肺」に働きかけ、身体を温めて、発汗作用を高め、体の中のものを外に発散させたり、体内の循環を良くする働きがあると考えられています。摂り過ぎると肝臓や目の不調に繋がり、筋肉の攣りを引き起こす場合もあります。
「辛」の主な食材
ショウガ、ネギ、ニンニク、ニラ、コショウ、サンショウ、トウガラシ、ワサビ など
「鹹味(かんみ)」
塩辛い味のことで、しょっぱい味というだけではなく、ミネラルが多くふくまれているもの、という意味があり、海藻類なども当てはまります。「腎」に働きかけ、体のしこりを取り軟らかくする作用、便通を促す作用、体を潤す作用などがあります。摂り過ぎると血圧が上がったり、下痢をしたりする場合があります。
「鹹」の主な食材
アサリ、シジミ、牡蠣、昆布、海苔、ヒジキ、味噌、天然塩 など
疲れた時に甘いものを食べたくなる、というような、自然に体が欲するものと考えればわかりやすいですね。体調に合わせて、五味を上手に取り入れることは大事ですが、それぞれ摂りすぎると、対応する臓に負担がかかるので、気を付けましょう。ただ、鹹味=ミネラル分に関しては、日本人は不足しがちと言われているので、積極的に摂ると良いです。毎日使う調味料をできるだけ自然に近い作り方で製造されているものを選ぶと、ミネラル分がアップ♪また、朝味噌汁にワカメをちょい足しするのもいい方法ですね~腎に働きかけて養うことは、老化防止につながります!
それでは食品のもう一つの役割「五性」についてお話ししますね~
五性
五性とは、食品が身体にどのように作用するかを表わしていて、寒、涼、平、温、熱という五つの性質に分けられます。体の余分な熱を取り興奮を静める「寒」と「涼」、体を温め気や血の流れをよくする「熱」と「温」、温めも冷ましもしない「平」に分けられ、「寒・涼」「熱・温」は、それぞれ冷たさや温かさの程度の差で分けられます。
温熱性
温性、熱性は、カラダを温める作用があり、辛い物や刺激のある食材が多いです。生姜、シナモン、山椒、にんにく、羊肉、鶏肉、黒砂糖、栗、長ねぎ、紅茶などが代表的な食材です。体を温めて、内臓の働きを活発にし、血や気の流れが促進され代謝も向上するといわれています。 白菜などの葉物野菜や大根、ゴボウなどの根菜類など、冬によく食べる野菜は、実は寒涼性の物が多いです。
寒涼性
寒性・涼性は、カラダを冷やす作用があり、夏が旬のもの、南国で採れるもの、といったイメージです。ニガウリ、キュウリ、ナス、トマト、レタス、豆腐、バナナ、梨、柿、緑茶、コーヒー、白砂糖などが代表的な食材です。体内で発生する炎症などを抑制し、血液浄化、解毒、利尿促進といった働きがあります。体内の老廃物を排出、除去する効果もあります。
平性
穏やかなな性質を持ち、滋養強壮に効果あるものが多いです。長いも、大豆、とうもろこし、じゃがいも、さつまいも、卵、クコの実、うるち米、はちみつ、黒きくらげ、ニンジンなどが代表的な食材です。
食材を調理・加工すると元々の性質から変化するということもあります。例えば、寒涼性の食材は、お鍋に入れるなど加熱調理することで平性寄りに変わるし、発酵食品は元の食材よりも温熱寄りになります。基本的には旬のものを食べることを意識し、冬は火を通した温かいものを、夏はみずみずしいお野菜をそのまま、というようにしていればオッケー♪。ただ、エアコンで体が冷えちゃった…というような状態の時は、季節より自分のお体に合わせた食事をしましょうね。また、流行の?スムージーは体を冷やす食材がぎっしり入ったものが多いです。冷え性に悩む女性が、体に良いからと朝、スムージーをがっつり飲むことは体をギンギンに冷やす行為(>_<)体質に合わせた食養生、大事ですね!
皆様も、季節や体質に合わせた「五味」「五性」を毎日の生活にゆる~く取り入れてみてくださいね~(^^)/
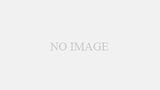
コメント